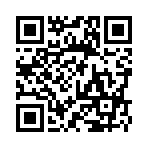2011年03月31日
土壌細菌による放射能の分解

原子爆弾を製造したアメリカの物理学者は、被爆地は100年の間人が住めない不毛の地と化し、植物は一切生息できないと予測していた。しかし広島では半年後には雑草が生え出し、その数ヶ月後には草花が生えて花が咲き、木の芽が出て、一年後には放射能レベルが激減し、人々が住めるようになりました。広島の土壌内の微生物および空中から運ばれる微生物(耐放射性菌)が、放射能を分解消失したと言われています。そうなんです。私たちが何かをしなくても地球はいずれ元に戻ります。
人間の思考力を越えた存在が自然界の中にはあるようです。
それらの土壌細菌と人が共生できれば今起きている事実はいずれ収まる事になります。
ただ人はその中で生き抜かなければなりません
それは、被曝をいかに最小限に抑えるかという事が大きなカギとなります。
ヨウ素とセシウムの違いは半減期のあるものと長期的に続き蓄積されるものの違いです。
マスクをしたり野菜を洗ったり水をろ過したりする事は決して恥ずかしい事ではありません
むしろ率先して使用する事で生き抜きましょう
Posted by 環マテ at 21:51│Comments(6)
│ひとりごと
この記事へのコメント
はじめまして、
大内 桃子と申します。
私は、今福島の原発から60キロの大玉村という米所に住んでいます。
放射能を大地から取り除けたらと想い、
セシュウムを吸い取ってくれるという菜の花 ひまわりを育て、
バイオエネルギーも作りだしてゆければ、さらに
いいかな?と思っていたのですが、
最後の絞り糟かすなどが、放射能のかたまりになってしまうようで
こまっています。
お話の耐放射性菌でこれらを分解することはできるのでしょうか?
その有効な方法などあったらどうぞ、教えてください。
よろしくお願いいたします・
大内 桃子と申します。
私は、今福島の原発から60キロの大玉村という米所に住んでいます。
放射能を大地から取り除けたらと想い、
セシュウムを吸い取ってくれるという菜の花 ひまわりを育て、
バイオエネルギーも作りだしてゆければ、さらに
いいかな?と思っていたのですが、
最後の絞り糟かすなどが、放射能のかたまりになってしまうようで
こまっています。
お話の耐放射性菌でこれらを分解することはできるのでしょうか?
その有効な方法などあったらどうぞ、教えてください。
よろしくお願いいたします・
Posted by 大内 桃子 at 2011年04月02日 03:01
大内様
地震に次ぐ原発事故、本当に大変ですが頑張ってください
耐放射性菌がどのような種類かは日本ではわかっていないと思いますが、広島や長崎の放射能の早期の分解能力から考えると確かに生育していたのではないかと思います。もう時間がたち放射線が検出できない地域では菌が自然淘汰しているかも知れませんが爆心地に近い畑の土に冬眠しているかも知れません私は菌の専門ではないのでこの程度の話しかできませんが申し訳ございません
ロシアの話では
チェルノブイリで放射線を食べる菌が見つかったそうです。
チェルノブイリで有害な放射線を食べて成長する菌が生まれていた。
その菌はチェルノブイリ原子炉の壁に育っているのを、ロボットによって回収されその菌は豊富にメラニン色素を含んでおり、その表面を紫外線から守っていた。科学者は3種類の菌である実験を行った。
通常、植物は葉緑素によって光エネルギーを吸収して成長する。
実験では回収した菌に日光の代わりに、有害な放射線を与えた。すると菌たちは驚くことにこれらを吸収し、成長していった。
という記事を見つけました。
もう少し詳しい内容を調査しますのでわかり次第連絡させて頂きます。
地震に次ぐ原発事故、本当に大変ですが頑張ってください
耐放射性菌がどのような種類かは日本ではわかっていないと思いますが、広島や長崎の放射能の早期の分解能力から考えると確かに生育していたのではないかと思います。もう時間がたち放射線が検出できない地域では菌が自然淘汰しているかも知れませんが爆心地に近い畑の土に冬眠しているかも知れません私は菌の専門ではないのでこの程度の話しかできませんが申し訳ございません
ロシアの話では
チェルノブイリで放射線を食べる菌が見つかったそうです。
チェルノブイリで有害な放射線を食べて成長する菌が生まれていた。
その菌はチェルノブイリ原子炉の壁に育っているのを、ロボットによって回収されその菌は豊富にメラニン色素を含んでおり、その表面を紫外線から守っていた。科学者は3種類の菌である実験を行った。
通常、植物は葉緑素によって光エネルギーを吸収して成長する。
実験では回収した菌に日光の代わりに、有害な放射線を与えた。すると菌たちは驚くことにこれらを吸収し、成長していった。
という記事を見つけました。
もう少し詳しい内容を調査しますのでわかり次第連絡させて頂きます。
Posted by 環マテ at 2011年04月02日 10:43
http://takashima.tidt.fool.jp/
大内様
上記のサイトに光合成細菌による放射能の分解の専門家を見つけました。
大内様
上記のサイトに光合成細菌による放射能の分解の専門家を見つけました。
Posted by 環マテ at 2011年04月02日 11:09
大内様
上記のサイトは検索してヒットしたものですが私は光合成細菌が放射能を分解するメカニズムをよく理解できません
水産関連の文献で海水中のアオサに放射線を吸着させたところ非常に吸着率が高い事がわかりました。ただし4日後には放射性物質を排出してしまうと言う事もわかりました。
3日間で別の容器に移し4日後にアオサを取り出しその海水を逆浸透膜で処理すれば処理できると思います。
アオサに近い藻類で淡水で生育できるものを捜してみます。
放射能は水に溶け込みやすいので溶け込んだものを藻類に吸着させる方法もありだと思います。
※ひまわりの絞り糟かすなどはコンクリートで封じ込めをすることが可能です。
上記のサイトは検索してヒットしたものですが私は光合成細菌が放射能を分解するメカニズムをよく理解できません
水産関連の文献で海水中のアオサに放射線を吸着させたところ非常に吸着率が高い事がわかりました。ただし4日後には放射性物質を排出してしまうと言う事もわかりました。
3日間で別の容器に移し4日後にアオサを取り出しその海水を逆浸透膜で処理すれば処理できると思います。
アオサに近い藻類で淡水で生育できるものを捜してみます。
放射能は水に溶け込みやすいので溶け込んだものを藻類に吸着させる方法もありだと思います。
※ひまわりの絞り糟かすなどはコンクリートで封じ込めをすることが可能です。
Posted by 環マテ at 2011年04月02日 13:44
当時は砂利道で現在はアスファルトやコンクリートだらけ、かなりの高濃度の放射能で状況的に同じとは言えませんが
希望の持てる情報ありがとうございました
希望の持てる情報ありがとうございました
Posted by アマネ at 2011年04月13日 05:48
アマネさん
おはようございます
乾燥に強い土壌細菌類には放射能に強い菌が多くいるようです。
単体だけの放線菌を作るのは大変なので三重県四日市市の新井さんに尋ねてみてはどうでしょうか?きっと何かを得ることができると思います。彼は四日市大学と土壌細菌の産学研究をしています。
下記に問い合わせ先を書きますね
有限会社ニュー・ウェル/紀緑屋
TEL(059)349-4500
FAX(059)349-4501
おはようございます
乾燥に強い土壌細菌類には放射能に強い菌が多くいるようです。
単体だけの放線菌を作るのは大変なので三重県四日市市の新井さんに尋ねてみてはどうでしょうか?きっと何かを得ることができると思います。彼は四日市大学と土壌細菌の産学研究をしています。
下記に問い合わせ先を書きますね
有限会社ニュー・ウェル/紀緑屋
TEL(059)349-4500
FAX(059)349-4501
Posted by 環マテ at 2011年04月13日 06:39